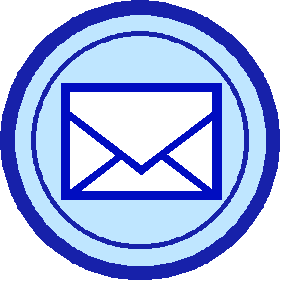禁治産者老人のした公正証書遺言を有効と認めた判例紹介2
*********************************************
(7) Aは、昭和57年8月6日、業者らの会合の席上、第一回目の脳梗塞発作を起こし、同月9日、大学病院に入院したが、これと入れ違いのように、控訴人の家族は、小牧市の家を引き払って、A宅に転居した。
その後、控訴人夫婦は、本件会社やAの印鑑、書類などを管理するようになり、その経営の実権を握ったことから、Cとの間で頻繁にトラブルが生じるようになり、ついにはCに対して仕事を与えず、給与も大幅に減額するといった事態も生じた。この間、Cの依頼を受けた晴昭やキクらが、控訴人夫婦に対して善処方を申し入れたことがあったが、同夫婦はこれに応じようとはしなかった。
なお、Aは、同年12月21日、症状が軽快して大学病院を退院したが、覇気が消え、仕事に対する関心も薄れた様子で、散歩をしたりテレビを見る以外は、寝ていることが多くなった。なお、Aは、昭和58年3月8日、公証人役場に赴いて公正証書遺言の作成を嘱託し、これに基づき第一遺言書が作成されている。
(8) Aは、昭和58年9月26日、心不全を起こして大学病院に二回目の入院をしたが、検査の過程で、第一回目の入院時とは異なる脳梗塞の部位が発見されており、その状態も、Bが誰か分からないほど悪化していた。
このような状態で、控訴人夫婦が本件会社やAの実印等を保管していることに不安を感じたBやCは、弁護士と相談の上、Aの財産保全を目的として、昭和58年10月21日、晴昭、キクらと共同して、Aに対する禁治産宣告の申立てを名古屋家庭裁判所岡崎支部にする(右申立てについては、F医師による精神鑑定を経て、昭和59年4月7日、Aを禁治産者とする旨の審判がなされ、控訴人らの不服申立てを経て、同年7月19日、確定している。)とともに、同年11月8日ころ、本件会社の取引金融機関に預金の解約等に応じないよう警告したり、市役所に印鑑証明の発行をしないよう要請するなどし、同月11日には、Bの名前で、亡失を理由として印鑑登録の抹消手続をした。
(9) このような動きを知った控訴人夫婦は、昭和58年11月11日夕刻、弁護士及び一代とともに大学病院に入院中のAを訪れ、Bの制止を無視して、前記申立てなどがなされたことと、このままでは本件会社の運営ができないことから、代表者を勉に変更することを求めたところ、Aは、右申立てについては不快感を示したが、代表者変更については、「そうかなあ。」と曖昧な返答をするにとどまった。
その後、A名義の代表取締役辞任届や大学病院での取締役会開催の議事録等が作成され、同月12日付けで勉が本件会社の代表取締役に就任した旨の登記がなされたが、右各書類のA作成部分の署名押印は、いずれもA自身によるものではなかった。また、同年12月22日付けで、本件会社の株主総会議事録及び取締役会議事録が作成され、これに基づいて勉が代表取締役に重任された旨の登記がなされたが、右議事録には大学病院に入院中のAが出席した旨記載されている上、A作成部分の押印は、A自身によるものではなかった。さらに、勉は、昭和59年1月17日、Aの代理人としてその印鑑登録手続を行ったが、その際に使用された代理権授与通知書のAの押印もA自身によるものではなかった。
(10) 勉は、昭和59年1月24日、本件会社の代表取締役として、取引金融機関に対する前記警告を理由として、Cに対し、懲戒解雇する旨の意思表示を行った。
また、Aは、本件各土地を含む19筆の土地及び建物三棟等の不動産を所有していたところ、控訴人夫婦らは、保管していたAの印鑑、登記済証などを用いて、これらの不動産につき、自分らを権利者として、昭和58年12月8日受付所有権保存登記、同月23日受付所有権移転登記、昭和59年3月30日受付条件付永小作権設定仮登記、同年4月7日受付根抵当権設定仮登記、同日受付賃借権設定仮登記、同年7月11日受付永小作権設定登記、同年9月13日受付所有権保存登記、同月25日受付所有権移転登記などを次々に経由したり、Aの有する本件会社の株式が控訴人夫婦や一代らに移転したことを示す書類を作成したりした。
(11) Aは、CやBらから控訴人夫婦による前記財産移転行為等を聞かされて立腹し、昭和59年1月29日ころ、Cに対する懲戒解雇の内容証明郵便の末尾に「甲野勉を新社長にする事はゆるさない 又社長にする許可も出していない」との文言を記載し、同年8月16、17日ころには、金庫の鍵や実印の返還を求めたり、土地の所有名義を変えたことについて非難する手記を作成し、さらに同年9月16日ころには、親戚に対して、自分の死後はBに全財産を渡すことを依頼する書類を作成するなどしている。
なお、控訴人夫婦は、Aの入院中、その入院費用を支弁していたが、終始付添いをしていたBらの生活費については、ほとんど支払うことがなく、見舞いも時々病室に顔を見せる程度であった。
(二) 以上の事実によれば、Aは、第二回目の入院までは、控訴人やその夫である勉に概ね好意的な姿勢を示しているのに対し、Cに対してはしばしば厳しい態度をしていたことが明らかである。したがって、Cに同情的な言動を示すことの多かったBに全財産を遺贈する旨の第二遺言の内容は、右時点までの経緯と符合しない印象を与えることは否定し難い。
しかしながら、Aは、いったん機嫌を損なうと、良好な関係にあって同居生活を送っていた控訴人夫婦に対しても、転居を余儀なくさせるほどの言動を示すことがあったのは前記認定のとおりである上、Aは、金銭面に細かく、全て自分の指図に従わなければ気がすまないワンマン的性格の持ち主であったから、前記のとおり、控訴人夫婦が、Aの第二回目の入院以降、その保管していた実印、登記済証などを利用して、本件会社の代表取締役変更の手続をしたり、A所有の財産の名義を次々に移転した事実を知って、控訴人夫婦に対する従来の好意的態度を変え、逆に、それまで、Aのワンマン的言動に耐え続けるほかなかったにもかかわらず、最後まで看護のために付き添っているBに感謝の念を抱くようになったと考えることにも相当の根拠があるというべきである。
そうすると、第二遺言の内容は、これに至るまでの全体の経緯と整合しない不合理なものとはいえず、Aが意思能力を欠いていたことを奇貨として、B及びC夫婦がなさしめたものであるとの控訴人の主張は採用できない。
二 争点2について
1 まず、控訴人は、第二遺言書は民法973条の要件を充たさない無効のものである旨主張し、これに沿う証拠として乙第三号証(承継前の一審原告が本件訴訟提起に際し、資格証明文書として提出したもの)を提出している。
しかしながら、証拠(甲第一号証、第四号証、第五号証の一、証人西川豊長)によると、第二遺言書の原本には、当初から、Aが、第二遺言当時、心神喪失の状況になかった旨の医師である立会人二名による付記及び同人らの署名押印がなされており、乙第三号証にこれがないのは、謄本作成時における公証人役場の過誤によるものであることが認められる。
そうすると、控訴人の右主張は、前提事実を欠くものであって、採用できない。
2 次に、控訴人は、第二遺言書は、公証人法36条九号の定める要件、すなわち、立会人二名(長坂及び山本の両医師)が立ち会った旨及びその事由並びにその年齢の記載を欠いているから無効であると主張する。
しかしながら、第二遺言書に記載された付記の内容に照らせば、右医師らが、民法973条の規定に基づく立会人として第二遺言に立ち会った事実を容易に認識することができるというべきである。
また、公証人法36条各号掲記の事項の記載を欠く証書がすべて無効となるわけではなく、その効力は、各事項の記載が要求されている趣旨によって個別的に判断されるべきであるところ、立会人の年齢の記載は、これにより立会人の特定を容易にすることに主たる目的があると考えられるから、第二遺言書のように、住所、職業など他の記載から右特定が十分に可能な場合は、年齢の記載を欠くからといって直ちに証書全体の無効原因となるものではないと解するのが相当である。よって、控訴人の右主張は採用できない。
3 さらに、控訴人は、公証人法35条により、第二遺言書を作成した公証人は、Aが禁治産者であることを証する書面を徴し、その時点でAが本心に復していたことを確認すべく立会医師から事情を聴取して、これらの事実を公正証書に記載すべきであるにもかかわらず、これらが尽くされていないと主張する。
しかしながら、公証人法35条は、公証人が証書を作成するに際し、「自ら」実験した事実を録取し、その方法を記載することを要求することによって、その責任の所在を明確にし、その作成過程に公証人以外の第三者が関与することによる過誤を未然に防止することを目的としているものと解される。
したがって、遺言公正証書に記載されるべき内容としても、民法が手続要件として定めるものでもって必要十分であり、これを超えて、実体要件が充足されていることを公証人が確信するに至った事実及びその過程の記載が求められるものではないから、控訴人の右主張は採用できない。
4 また、控訴人は、第二遺言については、証人としてK弁護士が立ち会っているところ、同人は、Bから訴訟委任を受けて代理人となっていた者であり、実質的にBと同視すべきであるから、遺言の証人欠格を定めた民法974条三号に抵触し、無効である旨主張する。
右条項が、当該遺言に関して強い利害関係を有する一定の者の関与を排除し、もって遺言者の意思が正しく遺言に反映されることを目的としていることは控訴人主張のとおりであるけれども、法律関係安定の見地からみて、右は制限的列挙と解すべきである(その性質上、方式の履践が不可能ないわゆる自然の欠格者を除く。)から、Bの訴訟代理人となっていたK弁護士が証人の一人となっているからといって、第二遺言が無効となるものではなく、控訴人の右主張は採用できない。
三 争点3について
控訴人主張の贈与契約締結の事実については、これに沿う証拠(乙第55ないし第57号証、第78号証、第81ないし第83号証、第86、87号証、第90号証)もある。
しかしながら、右各証拠によっても、右契約成立の際に書面が作成されなかったことが明らかである上、前記(一1(一))のとおり、Aは、金銭面に細かく、それまで他人に財産を譲渡するなどの行為をしたことがなかったこと、その直後に作成された第一遺言では、控訴人に財産全部を遺贈するとの内容になっており、生前に全財産を控訴人夫婦に贈与する旨の本件贈与契約の内容と抵触すること、現実にAの所有にかかる不動産に登記をしたのは、Aに対する禁治産宣告の申立てがなされた後のことで、控訴人主張の贈与契約成立日から相当な月日が経過していること、しかも、登記の内容は、用益物権、担保物権などが多く、所有権に関する登記でも、控訴人主張の贈与契約を登記原因とするものは見当たらないこと(このような登記がなされた理由につき、控訴人及び勉は、前掲各証拠において、贈与税、登録免許税の負担を考慮したものであり、司法書士の指導に従ったまでである旨弁解するが、その内容自体、著しく不合理で採用できない。)、証拠(乙第56号証)によると、A(法定代理人B)が控訴人夫婦らに対し、前掲各登記の抹消登記手続等を求めた別件訴訟において、控訴人夫婦は、当初、前掲各登記はAの所有財産が勝手に処分されないよう、Aから信託を受けてなしたものである旨主張していたことが認められること、以上のような事実を総合すれば、前掲の積極証拠は到底採用できるものではなく、他に控訴人主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
第五 結論
よって、被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官渡辺剛男 裁判官加藤幸雄 裁判官矢澤敬幸)