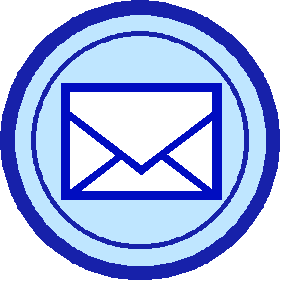賃貸建物敷金返還債務は建物相続承継者が承継するとした地裁判決紹介
○これに対し、Aの死亡により、本件建物に係る同人の持分権をその長男であるBが相続したことは当事者間に争いがなく、これにより、Bは、本件建物の単独所有者となり、同時に、その時点で、本件賃貸借契約における賃貸人たる地位もBのみが有することとなったのであるから、本件債務については、賃貸人であるBが承継すべきこととなり、被告が当然に敷金返還債務を法定相続分に応じて承継した旨の原告の主張には理由がなく、また、法定相続分割合で承継する旨の合意が成立したとも認めることはできないとして、原告の請求を棄却した令和元年7月31日大阪地裁判決(判時2460号73頁)を紹介します。
○この判決は控訴審令和元年12月26日大阪高裁判決でも維持されていますのでの別コンテンツで紹介します。
*********************************************
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、750万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、大阪市所在の建物(以下「本件建物」という。)の賃借人であった原告が、敷金として3000万円を差入れており、賃貸人であるA’ことAの相続人の一人である被告がそのうち750万円の返還債務を当然に相続した、又は、Aの相続人らの間で、法定相続分割合に応じて債務を承継する旨合意したと主張して、被告に対し、敷金返還請求権に基づき、750万円の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠等及び弁論の全趣旨によれば容易に認められる。)
(1)当事者等
原告は、飲食店の経営等を目的とする株式会社である。
原告の代表取締役を務めるBと被告とは、いずれも、Aの子である。Aは、平成26年5月11日に死亡したところ、同人は、韓国籍を有しており、同国民法の定めによれば、同人の法定相続人及びそれぞれの法定相続分は、次のとおりとされる。
長女 被告 28分の7
長男 B 28分の7
二女 C 28分の7
二男の妻 D 28分の3
二男の長男 E 28分の2
二男の長女 F 28分の2
(以下、上記6名を併せて「相続人ら」という。)
(2)本件賃貸借契約
本件建物は、大阪市天王寺区○○所在の3階建の建物であり、平成元年12月8日、当時の所有者より、Aが共有持分116分の96、Bが共有持分116分の20を取得する形で購入したものである。なお、A及びBは、同日、本件建物の底地についても同じ共有持分割合で購入した。
Bが代表取締役を務めていた原告、A及び個人としてのBは、同日、本件建物について、A及びBを賃貸人とし、原告を賃借人とする次の内容の賃貸借契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。)。原告、A及びBは、同日、敷金について、原告のAに対する貸付金のうち3000万円を敷金として振り替える形の処理を行った。
期間 平成元年12月8日から平成3年12月7日までの2年間
賃料 月額250万円(毎月末日限り当月分払い)
敷金 3000万円
(3)本件建物所有権の相続
Aは,平成26年5月11日、死亡した。Aの公正証書遺言には、本件建物の持分権について明確な記載はなされていなかったものの、平成27年1月23日、被告とBとの間では、本件建物に係るAの持分権は、相続によりBが取得するとの内容の裁判上の和解が成立している。
(4)相続税申告書の作成及び提出
被告及びBを含めた各相続人らは、平成27年3月11日、それぞれ、Aを被相続人とする相続税に係る申告書を提出した。いずれの申告書にも、「債務及び葬式費用の明細書」欄中「未払金」として、債権者を原告とする「預り保証金」3000万円の記載があり、同債務につき、被告、B及びCがそれぞれ750万円を、Dが321万4286円を、E及びFがそれぞれ214万2857円を負担することが確定した旨の記載(以下「本件記載」という。)がある。
(5)本件賃貸借契約の終了及び明渡し
本件賃貸借契約については、締結後、更新が重ねられ、Aが死亡した後も継続されていたが、原告、B及び平成27年12月15日にBから本件建物の持分2分の1を譲り受けたGは、平成29年4月30日、本件賃貸借契約を合意解約することとし、原告は、同日、本件建物を明け渡した。賃貸人の立場にあるB及びGから原告に対し、明渡しや原状回復義務の不履行があるとか、未払賃料がある旨の指摘はない。
2 争点
(1)Aの原告に対する敷金返還債務の28分の7を被告が相続したか
(原告の主張)
敷金返還債務も金銭債務であるところ、金銭債務のような可分債務については、被相続人の死亡により、遺産分割を待たずに法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継する。
Aの死亡により、原告に対する本件債務は当然に分割され、被告は、その28分の7を相続した。
(被告の主張)
敷金は、賃貸借契約に密接不可分に関連し、その発生、存続、終了に際して賃貸借契約に随伴し、これを離れては独立に存在する意義を有しない。遺言や遺産分割により賃貸物件を単独で取得した者がいる場合、その者が単独で賃貸人となり、賃借人に対して敷金の返還債務を負う。本件において、本件建物の所有権は、相続により、Bに移転しているから、本件債務もBに帰属しており、被告はその28分の7を相続していない。
(2)相続人らの間で、敷金返還債務を法定相続分に従って分割承継する旨の合意が成立したか
(原告の主張)
仮に、敷金返還債務が法定相続分に従って当然に分割承継されないとしても、次のとおり、B及び被告を含めた相続人間において、本件債務を法定相続分に従って分割承継する旨の合意が成立している。
すなわち、Aの死亡後である平成27年1月23日、相続人らそれぞれの代理人弁護士が集まり、H税理士を交えて相続税の申告書を作成するための協議を行った際、Bの代理人であるI弁護士は、Aの相続債務の欄に、本件債務の記載が漏れている旨指摘したところ、他の代理人らは、これに対して何ら異議を述べなかった。そして、その後、H税理士は、本件債務は法定相続分割合で承継すべきとするI弁護士の意見を、被告を含む他の相続人らの代理人に対して説明し、代理人らは、その意見に同意し、その結果、各相続人らにおいて、本件記載のある相続税申告書が作成された。
(被告の主張)
原告の主張する合意の成立については否認する。
本件において、相続人らの代理人弁護士間で協議が複数回行われたが、本件債務を分割承継するとの合意がなされたことは一度もなく、これが話し合われたこともない。
被告の相続税申告書に本件記載があることは認めるが、本件債務は、Bを除く相続人らにとっては詳細が不明であるところ、これを被告が承継するような動機は存在しない。このような債務について、具体的な協議が行われることもなく、合意文書も作成されないまま、申告期限が迫った相続税申告書に本件記載がなされることに異議を述べなかったことをもって、相続人間で分割承継の合意が成立していたとはいえない。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
前記前提事実に加え、証人H、後掲各証拠《略》及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)A死亡後の平成26年6月23日以降、相続人らそれぞれの代理人は、遺産の分配方法や日本と韓国それぞれで係属していた訴訟、両国における相続税の申告を含め、Aの相続に関する各種の問題への対応について、継続的に協議を行った。
(2)Aには、弁護士が成年後見人として選任されていたところ、同弁護士が平成26年6月27日に作成したAの財産目録には、本件債務の記載はなかった。
(3)相続人らそれぞれの代理人は、平成27年1月23日、H税理士の属する税理士法人が相続人ら全員からそれぞれ委任を受けることを前提に、H税理士を交えて、申告期限が同年3月11日に迫った日本における相続税の申告について、財産内容の確認を目的とする協議を行った。協議に先立ってH税理士が作成した財産の一覧表は、前記(2)の財産目録の記載に従って作成されていたため、本件債務が記載されていなかったところ、協議の場において、Bの代理人であるI弁護士は、同一覧表に漏れている相続債務がある旨指摘した。同日の協議においては、I弁護士から資料が提示されることはなく、代理人間で、漏れている債務の具体的な内容、金額やその分配方法についての協議はなされなかった。
H税理士を交えて相続人らそれぞれの代理人が集まり、財産内容の確認を目的とする協議を行ったのは、この日のみである。
(4)相続人らは、相続税申告に際し、それぞれ、必要な財産評価資料をH税理士に提出し、その中で、I弁護士は、本件賃貸借契約に係る契約書を提出した。平成27年3月5日、H税理士は、相続財産評価資料を添えて、同日時点における申告書案を被告の代理人に対して交付した。この時点での申告書案には、相続債務として本件債務3000万円の記載が加えられていたが、その具体的な負担者については空欄とされていた。
(5)H税理士は、平成27年3月9日までに、本件記載を含む形の相続人ら各人の相続税申告書案を作成し、被告の分を被告の代理人に対して交付した。被告の代理人は、被告の日本での相続税額が0円になることを確認した上、同日、被告から預かっていた印鑑を用いて相続税申告書に押印した。H税理士は、同月11日までの間に、被告以外の他の相続人らからも押印済みの相続税申告書を受領した上、同日、各相続人らの申告書を税務署に提出した。
上記の申告書完成に至る前、H税理士は、本件債務につきBが全額を負担する内容で申告書案を作成したものの、その内容にI弁護士から異議が述べられたことを受けて、H税理士は、他の代理人それぞれに連絡を取り、相続税の申告書を提出する上では法定相続分で申告することについて各代理人から了承を得た上で、前記のとおり、本件記載を含む内容で申告書を作成したとの経緯があった。
(6)Aの相続に係る被告及びBの日本における相続税額は、いずれも0円であった。
2 争点(1)について
原告は、敷金返還債務は金銭債務であるから、本件債務は、賃貸人であるAの死亡により、当然に法定相続分に応じて相続人らが分割承継した旨主張する。
しかし、敷金に関する法律関係は、賃貸借契約に付随従属するものであり、建物賃貸借契約において建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合、敷金に関する法律関係も、当然に新賃貸人に承継されるものと解されるところ(最判昭和44年7月17日・民集23巻8号1610頁参照)、相続により建物所有権の移転が生じて賃貸人たる地位の移転が生じた場合について、これと別異に解すべき理由はない。
本件において、Aの死亡により、本件建物に係る同人の持分権をBが相続したことは当事者間に争いがなく、これにより、Bは、本件建物の単独所有者となり、同時に、その時点で、本件賃貸借契約における賃貸人たる地位もBのみが有することとなったのであるから、本件債務については、賃貸人であるBが承継すべきこととなる。そうすると、本件債務について、被告が当然に法定相続分に応じて承継した旨の原告の主張は、理由がない。
3 争点(2)について
原告は、被告を含めた相続人らの間で、本件債務について、法定相続分割合で承継する旨の合意が成立した旨主張する。
しかし、前記認定のとおり、平成27年1月23日に相続人らの代理人らが集まった際には、本件債務について、承継割合を含めた具体的協議はなされておらず、この時点で、本件債務につき法定相続分割合で承継する旨の合意が成立したと認めることはできない。このことは、同日の協議に同席していたH税理士が、後に、本件債務をBが全額承継する内容の申告書案を作成したことに照らしても明らかである。
そして、その後、I弁護士から異議が述べられたことを受けて、最終的に、相続人らの申告書に法定相続分割合に従って承継する旨の本件記載がなされたことが認められるものの、H税理士は、その経緯について、申告書の記載としてそのようにすることについて他の相続人らの了承を得た旨述べるにとどまり、それ以上に、原告の主張するような、H税理士において、実際の債務負担額についてのI弁護士の意見を他の弁護士らに対して説明し、他の相続人らの代理人がこれに同意したとの事実については、これを認めるに足りる証拠はない。
相続税申告における被告の関心の中心は相続税額が0円になるか否かに向けられていたこと、相続人間で争いのある債務について法定相続分割合に従って相続税の申告を行う場合もあること等に照らすと、被告が本件記載のある相続税申告書を作成したことを殊更に重視することはできない。本件債務は、平成27年1月23日まで被告においてその存在を認識していなかったものであり、かつ、前記のとおり、当然に相続分割合に従って分割されるべきとは解されないものであるところ、本件債務の実際の負担額について具体的な協議がなされたことが認められない本件においては、相続税申告における本件債務に関する記載方法を超えて、その実際の負担割合も法定相続分割合とすることについて、少なくとも被告がこれに同意していたと認めることはできず、原告主張の合意が成立していたとは認められない。
4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 岡野慎也)