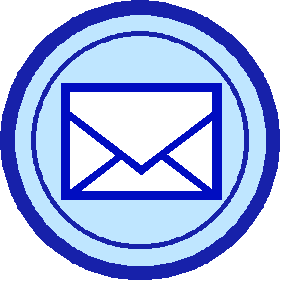遺言書成立日と異なる日付の自筆証書遺言を無効としない最高裁判決紹介
○事案は、遺言者Aが平成27年4月13日、入院先の病院において、遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日、弁護士の立会いの下、押印したというものです。この自筆証書遺言について、遺言書の完成した日は押印した5月10日のところ、実際、遺言書を作成した日は4月13日で、この遺言書は、真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効であると原審名古屋判決は結論付けていました。
○これに対し令和3年1月18日最高裁判決は、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないとして原審判決を破棄しました。
○自筆証書遺言での日付とその他の全文を書いた日が異なっている場合の遺言書の効力なんて考えたこともありませんでした。最終的に日付と署名・押印して完成し、その完成した日が遺言書作成日と思っていたからです。また、遺言書の内容文と日付・署名押印の時期がずれていることなど遺言書だけでは証明が困難です。
○しかし昭和52年4月19日最高裁判決は、建前論として「民法968条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならないことはいうまでもない。」としています。
○そこで遺言書本文を書いた日と日付が異なっていることが明らかな場合、遺言無効の可能性もあり、本件の争いが生じたわけですが、形式論を重視して無効としたのが名古屋高裁判決で、最高裁は、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するとして常識的判断に至りました。
○昭和52年最高裁判決も、遺言者が遺言書のうち日附以外の部分を記載し署名して印をおし、その8日後に当日の日附を記載して遺言書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らすと、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言として適式なものと解するのが、相当と常識的判断をしています。
****************************************
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
平成31年(受)第427号上告代理人○○○○ほかの上告受理申立て理由及び同第428号上告代理人○○○○ほかの上告受理申立て理由(ただし、いずれも排除された部分を除く。)について
1 本件の本訴請求は、亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について、被上告人らが、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して、上告人らに対し、本件遺言が無効であることの確認等を求めるものである。
2 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1) 被上告人らはAの妻であるX1及び同人とAとの間の子らであり、平成31年(受)第428号上告人ら(以下「上告人Y2ら」という。)はAの内縁の妻であるY2及び同人とAとの間の子らである。
(2) Aは、平成27年4月13日、入院先の病院において、本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日、弁護士の立会いの下、押印した。本件遺言の内容は、第1審判決別紙遺産目録記載の財産を上告人Y2らに遺贈し、又は相続させるなどというものであった。
(3) Aは、平成27年5月13日、死亡した。
3 原審は、上記事実関係の下において、次のとおり判断して、被上告人らの本訴請求を認容すべきものとした。
自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならず、本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきであった。自筆証書である遺言書に記載された日付が真実遺言が成立した日の日付と相違しても、その記載された日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が上記遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、上記の日付の誤りは遺言を無効とするものではないと解されるが、Aが本件遺言書に「平成27年5月10日」と記載する積もりで誤って「平成27年4月13日」と記載したとは認められず、また、真実遺言が成立した日が本件遺言書の記載その他から容易に判明するともいえない。よって、本件遺言は、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効である。
4 しかしながら、本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照)、前記事実関係の下においては、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。
しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。
5 以上によれば、本件遺言を無効とした原審の前記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり、原判決中本訴請求に関する部分は破棄を免れず、本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、これを原審に差し戻すのが相当である。そして、本件の反訴請求は、上告人Y2らが、被上告人らに対し、本訴請求において本件遺言が無効であると判断された場合に、予備的に、死因贈与契約の成立の確認等を求めるものであるところ、本訴請求について原判決が破棄差戻しを免れない以上、反訴請求についても当然に原判決は破棄差戻しを免れない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚)
*************************************
昭和52年4月19日最高裁判決(裁判集民事120号531頁)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人○○○○、同○○○○の上告理由一ないし四及び七について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができないわけではなく、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに帰し、採用することができない。
同五について
記録によれば、原審は所論の遺言書提出命令の申立につきこれを許すべきではないと認めて暗黙に却下したものと認められるから、右申立についてなんらの裁判をしなかつたとの論旨は理由がなく、また、原審認定の事実関係のもとにおいて右提出命令の申立を容れなかつた原審の判断に、所論の違法は認められない。
同六について
民法968条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺言書のうち日附以外の部分を記載し署名して印をおし、その8日後に当日の日附を記載して遺言書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らすと、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言として適式なものと解するのが、相当である。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切ではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 環昌一 裁判官 天野武一 江里口清雄 高辻正己 服部高顕)