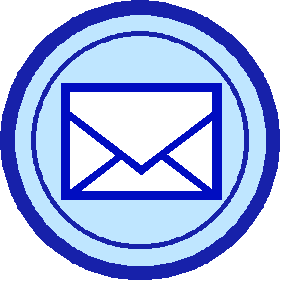遺言での錯誤は動機非表示でも要素の錯誤になりうるとした地裁判決紹介
○公正証書遺言の無効確認を求めたもので、結論としては、遺言者が各不動産についての真実の権利関係を知っていたならば、本件公正証書遺言の効力を維持するよりもあえてその効力を全く否定されることを望んだであろうことが明らかであるとはいえず、本件における遺言者の動機の錯誤は、要素の錯誤とは認められないとして棄却されました。
○しかし、遺言の錯誤を検討するに当たっては、遺言の意思表示は相手方のない単独行為であって、取引安全の要請はないこと、遺言における錯誤が要素の錯誤に当たるかどうかの判断においては、あくまでも当該遺言者のみを基準とすれば足り、錯誤がなかった場合に当該意思表示をしたかどうかを一般の通念を基準として検討する必要はないし、また、動機の錯誤においてその動機が表示されていなくても、要素の錯誤と認めることができる等重要な基準を説明しており、参考になります。
********************************************
主 文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
東京法務局所属公証人A作成の昭和59年第3688号遺言公正証書は無効であることを確認する。
第二 事案の概要
本件は、原告が、その弟である被告に対し、両名の亡母のなした遺言の無効の確認を求めた事案である。
一 争いがない事実
(中略)
二 原告の請求
本件公正証書遺言は、Dの錯誤によりなされたものである。また、Dは、その後、同遺言に抵触する内容の遺言をしており、これにより本件公正証書遺言は取り消されたものとみなされる。よって、本件公正証書遺言の無効の確認を求める。
三 争点
1 本件遺言がDの錯誤により無効であるか
(一) 原告の主張
本件公正証書遺言は、別紙物件目録一ないし六記載の各不動産がC死亡の時点において前記登記簿の記載のとおりの共有関係にあることを前提になされたものである。しかし、実際は右各不動産はいずれもCがその全部を所有していたのであるから、Dには、右遺言をするについて錯誤があった。
したがって、本件公正証書遺言は無効である。
(二) 被告の主張
争う。
(中略)
第三 争点に対する判断
一 争点1について
1 前記のとおり、本件においては、別紙物件目録一ないし六記載の不動産の真実の所有関係は、登記簿上の記載とは異なっていた。そして、Dは、本件公正証書遺言をなすに当たって、その対象となる右各不動産が登記簿の記載に従った持分割合により共有されていることを前提としていたものと推認できる。したがって、Dには、本件公正証書遺言をなすに当たって、その前提事実を誤認しており、動機の錯誤があったものと認められる。
2 そこでさらに、Dの右錯誤が要素の錯誤に当たるかどうかを検討する。
(一) 一般に、要素の錯誤とは、当該錯誤がなかったら、表意者はそのような意思表示をしなかったであろうし、一般の通念に照らしてもそうした意思表示をしないであろうようなものを指す。また、動機の錯誤は、そうした動機が相手方に表示された場合のみ、要素の錯誤となり得る。
しかしながら、遺言の意思表示は相手方のない単独行為であって、取引安全の要請はない。また、遺言の解釈における遺言者の最終的意思の尊重の趣旨からいっても、当該遺言者個人の内心の意図が重視されるべきである。
したがって、遺言における錯誤が要素の錯誤に当たるかどうかの判断においては、あくまでも当該遺言者のみを基準とすれば足り、錯誤がなかった場合に当該意思表示をしたかどうかを一般の通念を基準として検討する必要はないし、また、動機の錯誤においてその動機が表示されていなくても、要素の錯誤と認めることができるものと解すべきである。
(二) もっとも、遺言者の死亡後にその真意を解釈しようとする場合、遺言者自らが錯誤の主張をしているわけではないし、現在その真意を直接確認する方法がないのであるから、遺言者に軽微な前提事実の認識の齟齬が認められたとしても、そうした錯誤がなければ当該遺言がなされなかったはずであると安易に断定することはできない。
しかも、遺言者が既に死亡した状況においては、改めて異なった遺言をし直すことができず、遺言を無効とすれば、遺言が全くない状態に帰することとなるが、それがかえって、錯誤に基づく遺言の効力が維持される状態以上に、遺言者にとって望ましくないものであるということもあり得る。一般に、錯誤無効は表意者自身が主張する意思を有しない場合に第三者がこれを主張することは原則として許されないものとされている(最高裁判所昭和40年9月10日第二小法廷判決)ことに照らしても、右のような場合に遺言を無効とすることはできない。
したがって、要素の錯誤かどうかは、単に、かかる錯誤がなかったらそうした遺言をしなかったかどうかという観点から判断するのではなく、遺言者が真実の前提事実関係を認識していたならば、当該遺言の効力を維持するよりも、あえて遺言が全くない状態を望んだことが明らかかどうかという観点から判断すべきものと解するのが相当である。