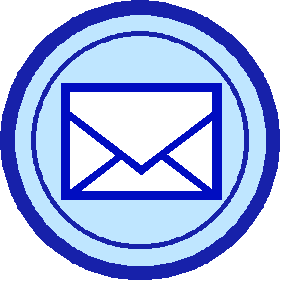全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言を無効とした地裁判決紹介
○亡竹子の相続人であると主張する原告が、亡竹子から弁護士である被告に現金だけで3億円を超える多額の遺産を遺贈することを内容とする本件遺言について、無効であることの確認を求めた事案についての平成25年4月11日京都地裁判決(判時2192号92頁)の関連部分です。
○判決は、秘密遺言証書封紙に自署し、本件遺言書が自己の遺言書である旨並びに自己の氏名及び住所を述べることができたとしても、平成17年10月3日当時、亡竹子に遺言能力がなかったものと認めるのが相当であり、本件遺言書は、秘密証書遺言としては無効であるとし、また、平成15年12月当時、亡竹子が、既に低酸素血症又はラクナ梗塞を原因とする血管性認知症又はアルツハイマー型認知症を発症していたことをあわせ考えるならば、本件遺言作成当時、亡竹子は、本件遺言がもたらす結果を理解する精神能力に欠けていたものと認めるのが相当であるから、本件遺言は、自筆証書遺言としても無効であるとしました。
○論点は多岐に渡りますが、遺言能力に関する判断部分を紹介します。
*********************************************
主 文
一 DF竹子が、平成17年10月3日に、京都地方法務局所属公証人E竹子梅夫に対し自己の遺言書である旨を申述した遺言書(平成17年第792号をもって秘密遺言証書封紙が作成されたもの)による遺言は、秘密証書による遺言としても、平成15年12月11日作成の自筆証書による遺言としても、無効であることを確認する。
二 参加費用は参加人の負担とし、その他の訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第一 事案の概要
一 原告の請求の趣旨
DF竹子が平成17年10月3日にした、次の二項掲記の秘密証書遺言は無効であることを確認する。
二 主文一項掲記の遺言の内容
主文一項掲記の遺言書(以下「本件遺言書」といい、これによる遺言を「本件遺言」という。)の記載内容は、下記のとおりであり、遺言者は、DF竹子という高齢女性(以下「竹子」という。)であった。
記
「ゆい言書
私の いさんは 後のことをすべて
おかませしている弁ご士、Bf
たろうにいぞうします
ゆいごんしっこうしゃは
CCまつおにおねがい
します 平成15ねん12月11日
DF竹子」
三 紛争の骨子
原告は、竹子の相続人であり、本件遺言が無効であると主張して本件訴訟を提起した。原告が相続人かどうかは争いがある。
被告は京都弁護士会所属の弁護士である。竹子は被告の依頼者であった。本件遺言により被告に遺贈された竹子の遺産は、預金だけで3億円を超える多額のものであった。
参加人は、本件遺言により遺言執行者として指定された者であり、京都弁護士会所属の弁護士である。
本件遺言書は、当初、民法968条所定の自筆証書であったが、後に、民法970条所定の秘密遺言証書封紙が作成された結果、秘密証書となった。
第二 前提事実
以下の事実は、争点摘示の前提となる事実である。証拠番号を掲記したものを含め、いずれも、当事者間に争いがないか、積極的に争うことが明らかにされない事実である。
一 身分関係等
(1)竹子は、大正5年3月3日生まれの女性であり、平成21年2月18日に92歳で死亡した。
(2)竹子は、竹子p春夫(文久元年生)とBN夏子(慶応元年生)の間の嫡出子として戸籍の届出がされた。竹子の兄弟として戸籍に記載があるのは、次の8名である。
(中略)
第三 争点
一 本案前の争点(訴えの利益)
原告が竹子の相続人かどうかが争点となる。
遺言の有効無効は、当該遺言によって法的地位の変動が生じた当事者間で争われる必要があり、それ以外の当事者間では、判決で当該遺言の有効無効を確定しても何ら法的紛争の解決に資することがない。このような場合、判決で遺言の有効無効を確定する(訴訟上の)利益を欠くから、裁判所は、このような類の訴えが提起されても、遺言の有効無効に関する審理も判決もすべきではないことになる。
もし、原告が竹子の相続人でないとすれば、本件訴えは、本件遺言の有効無効について検討を加えるまでもなく、不適法な訴え(訴えの利益を欠く訴え)として却下すべきことになる。
二 本案の争点(本件遺言の効力)
本件遺言の有効無効に関しては、次の(1)ないし(4)が争点である。
(1)本件遺言を秘密証書とするための方式が遵守されたかどうか。
(2)公証人に対する申述の当時(平成17年10月3日)の竹子の遺言能力
(3)本件遺言書作成の当時(平成15年12月11日)の竹子の遺言能力
本件遺言書は、自筆証書遺言の要式を充足しているため、本件遺言が秘密証書遺言として無効であったとしても、自筆証書遺言としての本件遺言の有効性が問題となるのである。
(4)本件遺言が公序良俗に反するものとして無効となるかどうか。
(中略)
理 由
第一 原告が竹子の相続人かどうかについて
(中略)
第六 遺言能力に関する当裁判所の判断
一 遺言能力の相対性について
民法は、近代法の大原則とされる「私的自治」を採用し、個人が自分の意思により(単独の意思表示又は相手方との合致した意思表示-契約により)、法律関係の発生・変更・消滅を具体的に規律することを認めるものであるが、それは、あくまで、正常な意思活動に基づく行動(意思表示)がされたことを前提とする。
認知障害を負う者は、私的自治の理念に適った行動ができないのであるから、その者の財産が私的自治の名の下に散逸してしまう危険まで民法が容認しているとは到底解されないからである。
したがって、民法には明示的な規定を欠くものの、意思表示がその本来の効果(表示された意思のとおりに法律関係が発生・変更・消滅するとの効果)を生ずるためには、その意思表示がもたらす結果を正しく理解する精神能力を有する者によってされる必要があり、その精神能力を欠く者がした意思表示は無効であると解されている。
すなわち、20歳以上の者であれば誰でも有効に契約を締結することができるわけではないし、15歳以上の者であれば誰でも有効に遺言ができるわけではない。意思表示を有効に行うための精神能力は「意思能力」と呼ばれ、遺言を行うのに要求される精神能力は特に「遺言能力」とも呼ばれる。
意思表示が、どの程度の精神能力がある者によってされなければならないかは、当然のことながら、画一的に決めることはできず、意思表示の種別や内容によって異ならざるをえない(意思能力の相対性)。
単純な権利変動しかもたらさない意思表示の場合(日常の買い物など)、小学校高学年程度の精神能力がある者が行えば有効であろうが、複雑あるいは重大な権利変動をもたらす意思表示の場合、当該意思表示がもたらす利害得失を理解するのにもう少し高度な精神能力が要求されるから、小学校高学年程度の精神能力しかない者が行った場合、意思能力の欠如を理由に意思表示が無効とされることが多いものと思われる。
二 公証人への申述(平成17年10月3日)当時の遺言能力について
(1)前記第三の四に認定の事実(西陣病院入院時の竹子の状態)、第三の六に認定の事実(二回目の京都第一赤十字病院入院時の竹子の状況)、前記第四の三に認定の事実(在宅介護の指示書の内容)に加え、前記第五の医学的知見を総合すれば、本件遺言書が自己の遺言書である旨をE竹子公証人に申述した平成17年10月3日の時点までに、竹子には、認知症の中核的な症状が非常に顕著に現れていたことが明らかである。
医療従事者や在宅介護従事者によって観察された竹子の認知症の症状に照らせば、竹子には、小学校高学年の児童程度の精神能力があったとも到底考えられない。
(2)実際にも、秘密証書遺言手続がされた前後2年ほど(平成17年2月18日から平成18年12月25日)までの間、竹子の預金が6000万円以上も払戻しがされているのに、その事実に関する竹子の態度(被告、竹子m、訴外会社の人間に預金の状況を尋ねた、あるいは定期的に報告させていた、あるいは預金が大きく減少した理由を問い質した等)がどの証拠からも伝わって来ないことは、平成17年10月当時、竹子が既に、財産を管理したり費消しようとする精神能力を欠いていたことをうかがわせるところである。
(3)また、竹子の認知症の症状は脳の病変に基づくものであるから、自分の立場、自分の置かれた状況、自分と周囲の者との関係性が正常に理解できないといった竹子の精神状態(医療従事者や在宅介護従事者が観察していた竹子の状態)は、落ち着いているように見える場合であっても変わりはないと考えざるをえない。
(4)したがって、仮に、秘密遺言証書封紙に自署し、本件遺言書が自己の遺言書である旨並びに自己の氏名及び住所を述べることができたとしても、平成17年10月3日当時、竹子に遺言能力がなかったものと認めるのが相当であり、本件遺言書は、秘密証書遺言としては無効である。
三 竹中貞信医師の証言について
竹中貞信医師は、西陣病院退院後の竹子の症状について、要旨「竹子について認知症を疑ったことはない。西陣病院の竹中信也医師が竹子をアルツハイマー病と診察したことは誤りであり、同病院での竹子の行動は竹子のわがままな性格によるものである。指示書にアルツハイマー病と記載したり、痴呆の状況を『〈1〉』あるいは『〈4〉』と記載したのは、訪問介護ステーションからそのような記載をしてほしいと頼まれたからである。短期記憶がなければ認知症の初期症状といえるが、京都市の訪問調査については、介護保険の介護度の関係で大げさに書かれたものであると思う」と証言する。
しかし、西陣病院での竹子の様子は、無理矢理自宅に帰ろうとしただけでなく、多量の失禁や昼夜逆転がみられ、夜間には猫や犬の幻覚をみていたというのである。前記第五の医学的知見に照らせば、これらは夜間せん妄等の認知症の症状とみるのが相当であり、単に竹子のわがままな性格に起因する言動とみるのは相当ではない。また、介護保険の要介護認定に携わる自治体職員は、介護・介助の要否及び必要程度を知るための相応の訓練を経て現場に臨んでいるはずであるから、介護・介助の必要程度を大げさに表現したいため、認知症の症状がみられないのに認知症の症状があると評価するとは容易に考えがたい。
したがって、上記二の判断と矛盾する竹中貞信医師の証言は直ちに採用することができない。
四 本件遺言書作成(平成15年12月11日)当時の遺言能力
(1)前記のとおり、平成17年10月当時、竹子が認知症の中核的な症状が顕著であり、西陣病院のMRI検査の結果や診断結果からも明らかなとおり、竹子の認知症の症状は、胸の病変に由来するのである。
そして、〔1〕低酸素血症と診断され、平成14年1月から自宅で介護を受けながら在宅酸素療法を続けていたこと、〔2〕平成14年10月8日のMRI検査でラクナ梗塞が認められること、〔3〕遅くとも平成14年12月ころから尿失禁や味覚障害といった認知症の初期症状がみられたこと、〔4〕介護保険の要介護認定のための訪問調査において、痴ほう性老人の日常生活自立度が、平成14年11月11日時点で「〈1〉」、平成15年11月11日の時点で「〈2〉b」とされていたこと、〔5〕平成15年11月11日時点では、短期記憶もできず、夜間不眠・昼夜逆転があり、ひどい物忘れがあるとされたことを総合すれば、竹子は、本件遺言書作成の当時、既に、低酸素血症又はラクナ梗塞を原因とする血管性認知症あるいはアルツハイマー型認知症を発症しており、初期認知症の段階にあったと認めるのが相当である。
(2)初期認知症の状態の者については、一律に意思能力・遺言能力が否定されるわけではないものと考えられる。遺言がもたらす結果が単純なものである場合(遺言の文面が単純かどうかではない。)、それほどの精神能力までは必要とされないであろうから、そのような遺言との関係では、初期認知症の状態にある者の遺言能力は直ちに否定されないものと思われる。
(3)しかしながら、本件遺言は文面こそ単純ではあるが、数億円の財産を無償で他人に移転させるというものであり、本件遺言がもたらす結果が重大であることからすれば、本件遺言のような遺言を有効に行うためには、ある程度高度の(重大な結果に見合う程度)の精神能力を要するものと解される。
(4)また、本件遺言は文面こそ単純であるが、本件遺言が訴外会社の経営にもたらす影響はかなり複雑である。
本件遺言をすると、〔1〕呉服業界に知識のない被告が経営を差配する可能性がある、〔2〕被告がCfと仲違いした場合、経営を良く知るCfが更迭されてしまう、〔3〕Cfが経営移譲を受けようとしても、贈与税や譲渡代金の負担が発生するため、被告からCfに株式譲渡が困難となる、〔4〕被告が死亡すれば被告の相続人が訴外会社の株主になる、という様々な事態が予想される。
(5)上記(3)及び(4)の事情を考慮するならば、小学校高学年レベルの精神能力がありさえすれば、本件遺言に関する遺言能力が肯定されるとすべきではない。そうでなければ、私的自治の理念に適った行動ができない者の思慮不足な行動を、私的自治の名の下に放置してしまう危険が大きいと思われる。
本件遺言に関する遺言能力は、もう少し高い精神能力-ここでは仮に「ごく常識的な判断力」と表現する-が必要というべきである。
(6)ところで、竹子は、被告に訴外会社の経営を委ねるつもりなどなく、本件遺言書を作成した約4か月後(平成16年4月)、Cfを呼び出し、将来の訴外会社の経営を任せる旨を伝えている。竹子は、Cfを後継者にする意図を有していたのであり、被告に訴外会社の経営者になって欲しくて本件遺言をしたのではないのである。
Cfを後継者にしようと考えるなら、被告に全資産を遺贈するといった遺言などしないのが当たり前であり、もし、そのような遺言をしていたなら、遺言を変更するか、本件株式だけでも生前にCfに贈与するかしたはずである。
竹子に「ごく常識的な判断力」さえあれば(正確な法的知識がなくとも)、本件遺言の内容を思い出し、本件株式まで被告に渡してしまうことが不都合ではないかという心配-Cfへの株式移転に支障が生じるのでは、あるいは被告が死んだら誰が株主になるのだろうといった程度の心配-が浮かんでくるはずであり,そうすると、竹子は、その心配を、わきまえのある者(被告やEO税理士)に相談し、問題を解決しようとしたはずである。
(7)ところが、前記第二に認定の事実経過に照らせば、竹子は、Cfを後継者にするには不都合な遺言をしているのに、全く心配をしていない(心配をしたなら、被告やEO税理士に本件遺言に関する相談をもちかけたはずなのにその形跡が全くうかがえないのである。)。したがって、竹子は、本件遺言をした場合の利害得失を「ごく常識的な判断力」のレベルでさえ、全く理解していなかったものといわなければならない。
(8)さらに、訴外会社は、竹子の親戚であるCfが経営の片腕となっており、同じく竹子の親戚である原告が中心店舗(祇園店)の店長になっていて、同族的色合いが濃い会社であるのに、なぜ、縁のある親戚に対しては、本件株式はおろか、会社経営の基盤となり得る預金さえも全く遺そうとはせず、赤の他人の被告に本件株式を含む全遺産を遺贈しようというのは、竹子の生活歴からすれば、いかにも奇異なことである。
竹子は、死後に入る墓の件で竹子p家に縁を感じていたことが明らかであり、四郎や原告のように、長らく親しくしていた親戚に何も財産を遺そうとしなかったというのも、やはり、かなり奇異なことといわざるをえない。
このことは、竹子が、本件遺言がもたらす利害得失を理解する能力が著しく減衰していたことを示す一つの事情となり得ると思われる。
(9)上記(3)ないし(8)の事柄に加え、竹子が、平成15年12月当時、既に、低酸素血症又はラクナ梗塞を原因とする血管性認知症又はアルツハイマー型認知症を発症していたことをあわせ考えるならば、本件遺言書作成当時、竹子は、本件遺言がもたらす結果を理解する精神能力に欠けていたものと認めるのが相当である。
したがって、本件遺言書は、平成15年12月11日作成の自筆証書遺言としても無効である。
五 よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 橋詰均 裁判官 合田顕宏)
裁判官吉岡真一は、転補のため、署名押印することができない。(裁判長裁判官 橋詰均)
別表(省略)